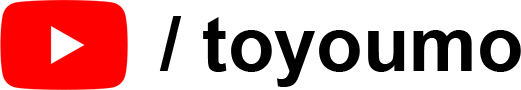眠りなサイエンス
睡眠博士ねねNene
vol. 6欧米と日本の睡眠習慣の違い
日本もすっかり欧米型の生活スタイルが定着し、ベッドでお休みになる方も多くなりました。しかし家に上がるときは、今も靴を脱ぐ方が大多数ではないでしょうか。日本人の感覚に合う習慣と、そうでないものを自然に選別しているようです。そこで今回は、欧米と日本の睡眠習慣の違いについてお話ししたいと思います。
親子関係と夫婦関係、どちらを優先するか?
 欧米と日本の眠りに関する習慣の違いとして、よく挙げられるのが親子で一緒に眠るかどうかだと思います。「川の字」になって寝るのは、子育て世代の日本人にとってはごくごく当たり前の光景です。ところが「個」を重視する欧米では、自立を促すために幼児であっても個室で寝かせるのが一般的です。
欧米と日本の眠りに関する習慣の違いとして、よく挙げられるのが親子で一緒に眠るかどうかだと思います。「川の字」になって寝るのは、子育て世代の日本人にとってはごくごく当たり前の光景です。ところが「個」を重視する欧米では、自立を促すために幼児であっても個室で寝かせるのが一般的です。
親子で一緒に眠るとスキンシップが図れ、子どもが親の愛情を感じることができて良いと言われます。その反面、それ以外の時間にきちんと親子で触れ合う時間が持てていれば、寝るときまで一緒でなくても特に問題はないとの意見もあります。
一方、これは夫婦の捉え方の違いの表れでもあります。日本では子どもが生まれると、子どもを基準に「お父さん・お母さん」という関係性になりがちですが、欧米では夫婦はあくまで「夫妻」。父である前に夫であり、母である前に妻であること優先するため、寝室を共にしています。
いずれにしても、家庭において睡眠は単に眠るだけでなく、親子間や夫婦間の絆を深める大切なコミュニケーションの場であると言えそうです。
どこでも寝られる日本人
 日本では電車の中などで居眠りをしている人をよくみかけます。もちろん私も経験があります。ところがこの様子は、世界的には非常に珍しいことで、しかも勤勉な国民性だと思っていた日本人が、仕事中や授業中でも構わず居眠りをする姿は、外国人に少なからず衝撃を与えているようです。
日本では電車の中などで居眠りをしている人をよくみかけます。もちろん私も経験があります。ところがこの様子は、世界的には非常に珍しいことで、しかも勤勉な国民性だと思っていた日本人が、仕事中や授業中でも構わず居眠りをする姿は、外国人に少なからず衝撃を与えているようです。
日本の生活文化を研究しているケンブリッジ大学准教授のブリギッテ・シテーガ氏は、『睡眠文化を学ぶ人のために』に寄せたコラムでこう書いています。「公の場での眠りには、目をつぶることで社会生活から自分を遠ざける、言い換えれば『社会的に不在になる』という機能がある」。礼儀正しい国民性だからこそ、息抜きとしての居眠りが生まれたのではないかとシテーガ氏は考察しています。
「寝姿」を他人に見られても平気な国民性
 日本人が公の場で居眠りができるのは、治安が良いという点も理由に挙げられると思います。それともうひとつ、そもそも「眠る」という行為に対する欧米諸国との感覚の違いも挙げられるようです。
日本人が公の場で居眠りができるのは、治安が良いという点も理由に挙げられると思います。それともうひとつ、そもそも「眠る」という行為に対する欧米諸国との感覚の違いも挙げられるようです。
例えばフランス人は、眠りはプライベートなものであり、恋人や夫婦以外の人と同じベッドに入ることに抵抗感を持つことに加え、寝姿を他人に見せることも恥ずかしい行為と感じるそうです。
一方日本人は、前述した「川の字」に代表されるように、パートナー以外の人とも寝室を共にすることが珍しくありません。
旅館などに泊まれば、複数の同行者と同じ部屋にふとんを敷いて一緒に眠ることが当たり前です。寝ている姿を他人に見られることに抵抗が少ないことも、「居眠り文化」が定着した一因と言えるでしょう。
シエスタは不要でも、仮眠は必要!?
1日における睡眠の取り方は、大きく3種類に分けられるようです。まずは1日に1回だけ眠る「単相睡眠」。北米や欧州の多くの国は、単相睡眠です。しかし一部の国には、「二相睡眠」と呼ばれる1日2回眠るパターンもあります。これが2つ目。その代表が、スペインなど主に地中海周辺で見られる昼寝の習慣「シエスタ」です。また意外かもしれませんが、中国にも似たような習慣があります。とはいえ近年、シエスタが長く生活の一部となってきたスペインでさえ、産業面での生産性向上などを理由にシエスタ廃止の動きが広まっています。
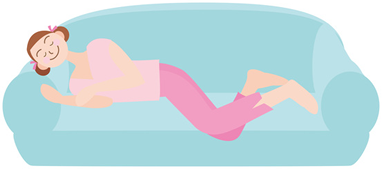 そして3つ目は、好きな時間に仮眠をとる「多相睡眠」。日本人の中にもみられる、通勤電車の中で眠るなど日に何度も睡眠を取る人が、まさにこの部類に当てはまります。
そして3つ目は、好きな時間に仮眠をとる「多相睡眠」。日本人の中にもみられる、通勤電車の中で眠るなど日に何度も睡眠を取る人が、まさにこの部類に当てはまります。
睡眠は、気候風土や社会制度などにも左右されるので、一概にどの睡眠がいいと決められるものではありませんが、ひとつ注目したい点があります。それは、シエスタが廃止されている一方で、欧米企業が積極的に仮眠の導入を始めている例があるということ。まさにvol.3でご紹介した「パワーナップ」です。シエスタのような長い昼寝は生産性の妨げになるけれど、20分以内の仮眠なら、むしろその後のパフォーマンスが上がる分、効率的ということでしょう。睡眠にも合理性を求める時代になっていることを感じます。
おやつとコーヒーブレイク
午後の強い眠気に対して、シエスタのように眠ってしまう方法を取る人たちがいた一方で、どうにか眠気をやり過ごそうと工夫した例もあります。単相睡眠圏の欧米で行われてきた午後の休憩「コーヒーブレイク」です。
 そして日本にも、同じような習慣がありました「おやつ」です。午後2時から4時ごろを「八時(やつどき)」と言ったことから、この時間の休憩やその際に食べたお菓子をおやつと呼ぶようになりました。あごを動かすことは覚醒作用があることから、お菓子をつまむことは理にかなっているんですね。
そして日本にも、同じような習慣がありました「おやつ」です。午後2時から4時ごろを「八時(やつどき)」と言ったことから、この時間の休憩やその際に食べたお菓子をおやつと呼ぶようになりました。あごを動かすことは覚醒作用があることから、お菓子をつまむことは理にかなっているんですね。
午後2時から4時ごろに起こる眠気は、ビジネスの現場にとっては作業効率の妨げとなり、また居眠り運転などによる交通事故が増えることからも、その対策は重要だと言えます。仮眠を取ったり、おやつを食べたり、世界の習慣を参考にご自身に合ったものを取り入れてみてはいかがでしょうか。
 vol. 1寝つきの悪さの原因と対策
vol. 1寝つきの悪さの原因と対策 vol. 2食生活と眠りの関係
vol. 2食生活と眠りの関係 vol. 3短期的な睡眠不足を乗り切る裏ワザ
vol. 3短期的な睡眠不足を乗り切る裏ワザ vol. 4睡眠不足が脳と体の成長に与える影響について
vol. 4睡眠不足が脳と体の成長に与える影響について vol. 5睡眠で分かるカラダ不調のサイン
vol. 5睡眠で分かるカラダ不調のサイン vol. 6欧米と日本の睡眠習慣の違い
vol. 6欧米と日本の睡眠習慣の違い vol. 7寝つきと寝起きのひと工夫
vol. 7寝つきと寝起きのひと工夫 vol. 8いびきが起きる原因と解消法
vol. 8いびきが起きる原因と解消法 vol. 9寝坊の原因と解消法
vol. 9寝坊の原因と解消法 vol. 10赤ちゃんとお子さんのより良い睡眠のために
vol. 10赤ちゃんとお子さんのより良い睡眠のために vol. 11目覚めに体がイタイのはこんな理由かも?
vol. 11目覚めに体がイタイのはこんな理由かも? vol. 12良い目覚めと悪い目覚めの違い
vol. 12良い目覚めと悪い目覚めの違い vol. 13仮眠や昼寝を効率よく取るコツ
vol. 13仮眠や昼寝を効率よく取るコツ vol. 14睡眠不足のリスク
vol. 14睡眠不足のリスク vol. 15健康習慣をおさらいしよう!
vol. 15健康習慣をおさらいしよう! vol. 16睡眠障害とは?
vol. 16睡眠障害とは?
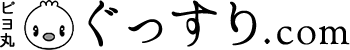
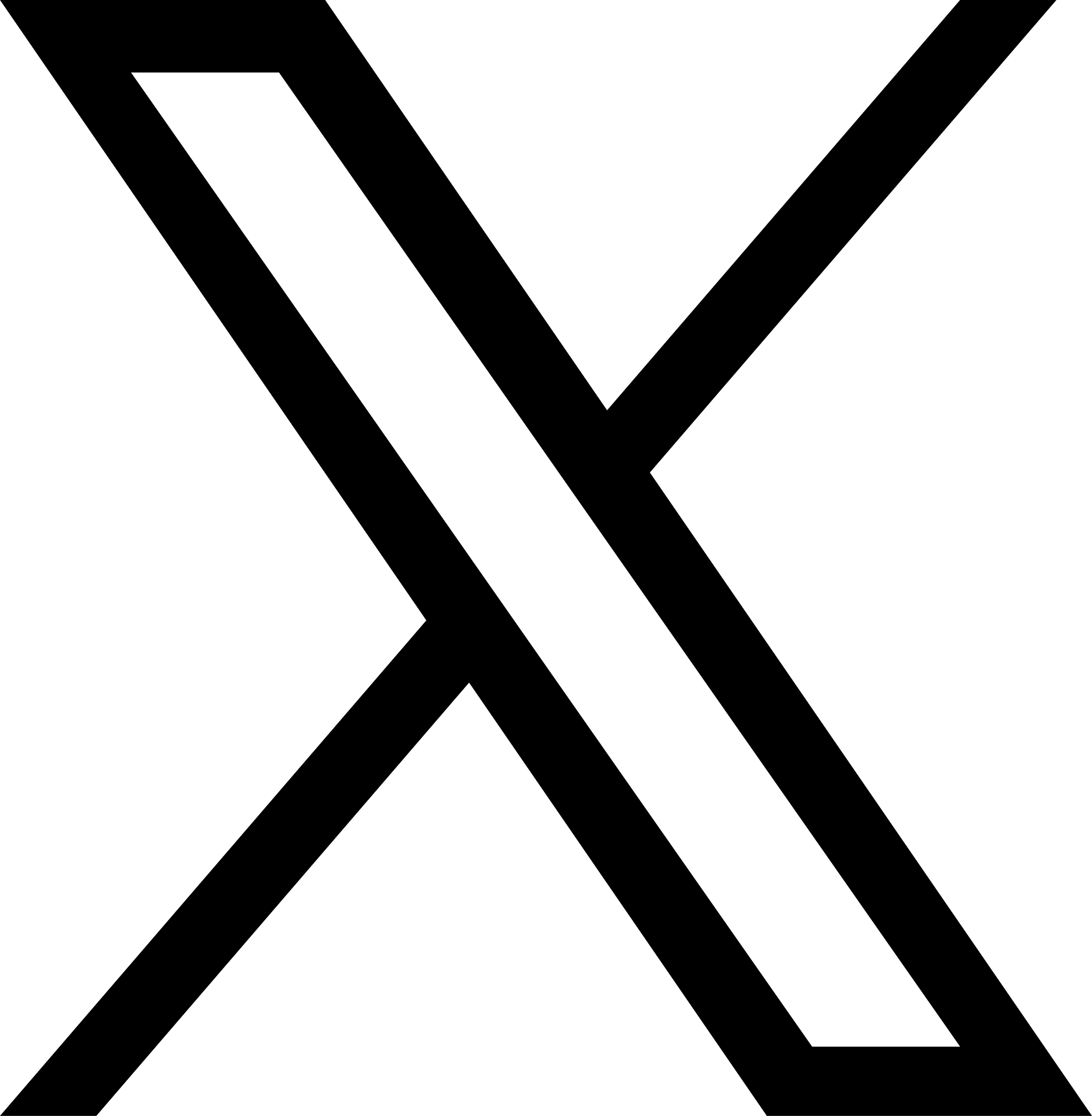




 【食後10分間エクササイズ】血糖値の上昇を抑えて老化防止
【食後10分間エクササイズ】血糖値の上昇を抑えて老化防止