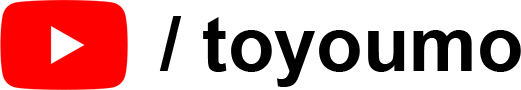眠りなサイエンス
睡眠博士ねねNene
vol. 2食生活と眠りの関係
厚生労働省が2019年に行った「国民健康・栄養調査」によると、生活習慣病のリスクを高める量を飲酒している人の割合は、男性14.9%、女性9.1%。また喫煙者の割合は、男性が27.1%、女性は7.6%でした。飲酒や喫煙は眠りと大いに関係しています。そこで、今回は「食生活」と「睡眠」のお話です。
朝食が“体内時計”の働きを整える
 「これを食べればよく眠れる!」と言える食べ物は、残念ながらありません。眠りをサポートする成分は報告されていますが、食事で効果を得るには、その成分を含む食材を大量に食べなければならず、現実的ではありません。まずは三大栄養素の糖質・脂質・タンパク質を含む、バランスの良い食事を心がけましょう。
「これを食べればよく眠れる!」と言える食べ物は、残念ながらありません。眠りをサポートする成分は報告されていますが、食事で効果を得るには、その成分を含む食材を大量に食べなければならず、現実的ではありません。まずは三大栄養素の糖質・脂質・タンパク質を含む、バランスの良い食事を心がけましょう。
むしろ注目してほしいのは、規則正しい食事。中でも朝食です。私たちの体には体内時計がありますが、実は時計はひとつではありません。脳にある親時計に加えて、細胞一つひとつにも時計遺伝子があることがわかってきました。内臓にも時計があり、朝食はそのリズムを整える助けになります。また毎朝食事をするためには、きちんと起きなければならず、自然と起床時間も整ってきます。起床時間を一定にすることは、夜ぐっすり眠るカギ。朝ご飯で内臓時計と生活サイクルを整えて、夜の心地よい眠りにつなげましょう。
食事の時間を体が学習!?
前段で朝食の大切さをお話ししましたが、朝食に限らず、1日の中でいつ食事をするかは重要なポイントです。
寝る直前に物を食べると、消化のために胃腸が活発に動き、眠りの質を下げてしまいます。また、日々決まった時間に食事をしている人は、その時間になると空腹を感じるようになってくるそうです。つまり、毎日遅い時間に食事をしていると、次第にその時間に合わせて体が食べる準備を始め、覚醒状態になってしまうと言うのです。夜の眠りを妨げないために、就寝する3~4時間前には食事を済ませるようにしましょう。
コーヒー、タバコはやっぱりNG!
 コーヒーやお茶などに含まれるカフェインに覚醒作用があることは、みなさんご存じだと思います。覚醒作用は、摂取後20~30分くらいで効き始め、若年者では3~4時間、高齢者では更に長い時間持続します。そのメカニズムは、疲れてくると脳細胞に睡眠物質であるアデノシンが溜まり、睡眠中枢に「眠れ!」と伝達します。この伝達をカフェインはブロックしてしまうのです。
コーヒーやお茶などに含まれるカフェインに覚醒作用があることは、みなさんご存じだと思います。覚醒作用は、摂取後20~30分くらいで効き始め、若年者では3~4時間、高齢者では更に長い時間持続します。そのメカニズムは、疲れてくると脳細胞に睡眠物質であるアデノシンが溜まり、睡眠中枢に「眠れ!」と伝達します。この伝達をカフェインはブロックしてしまうのです。
また、カフェインには血管拡張作用もあるため、内臓の血液循環が活発になり利尿作用を生じます。せっかく眠っても、トイレに行きたくなって目が覚めてしまい、満足な眠りが得られないことになりかねません。
 一方、昨今の禁煙ブームで肩身が狭くなっている喫煙者のみなさんに追い打ちをかけるようですが…眠りに関してもタバコはNG! カフェイン同様、ニコチンにも覚醒作用があるので夕食以降は控えた方がよいでしょう。
一方、昨今の禁煙ブームで肩身が狭くなっている喫煙者のみなさんに追い打ちをかけるようですが…眠りに関してもタバコはNG! カフェイン同様、ニコチンにも覚醒作用があるので夕食以降は控えた方がよいでしょう。
毎日の寝酒はアルコール依存症の入口!?
フランスの製薬会社が、かつて世界10ケ国で行った調査の結果、他国の人と比べて日本人は寝酒に頼る人の割合が高いことがわかりました。
確かにアルコールを飲むと寝つきはよくなりますが、睡眠後半においては、眠りが浅くなり中途覚醒が多くなることがわかっています。また寝酒を毎晩行うと、アルコールに対して次第に耐性ができて酒量が増えていき、最悪の場合アルコール依存症になる可能性があります。
習慣的な寝酒は、眠りを妨げる上に、健康にも悪影響を及ぼしかねないのです。1日も早く、お酒に頼らない寝つき対策にシフトチェンジすることを強くおすすめします。
 vol. 1寝つきの悪さの原因と対策
vol. 1寝つきの悪さの原因と対策 vol. 2食生活と眠りの関係
vol. 2食生活と眠りの関係 vol. 3短期的な睡眠不足を乗り切る裏ワザ
vol. 3短期的な睡眠不足を乗り切る裏ワザ vol. 4睡眠不足が脳と体の成長に与える影響について
vol. 4睡眠不足が脳と体の成長に与える影響について vol. 5睡眠で分かるカラダ不調のサイン
vol. 5睡眠で分かるカラダ不調のサイン vol. 6欧米と日本の睡眠習慣の違い
vol. 6欧米と日本の睡眠習慣の違い vol. 7寝つきと寝起きのひと工夫
vol. 7寝つきと寝起きのひと工夫 vol. 8いびきが起きる原因と解消法
vol. 8いびきが起きる原因と解消法 vol. 9寝坊の原因と解消法
vol. 9寝坊の原因と解消法 vol. 10赤ちゃんとお子さんのより良い睡眠のために
vol. 10赤ちゃんとお子さんのより良い睡眠のために vol. 11目覚めに体がイタイのはこんな理由かも?
vol. 11目覚めに体がイタイのはこんな理由かも? vol. 12良い目覚めと悪い目覚めの違い
vol. 12良い目覚めと悪い目覚めの違い vol. 13仮眠や昼寝を効率よく取るコツ
vol. 13仮眠や昼寝を効率よく取るコツ vol. 14睡眠不足のリスク
vol. 14睡眠不足のリスク vol. 15健康習慣をおさらいしよう!
vol. 15健康習慣をおさらいしよう! vol. 16睡眠障害とは?
vol. 16睡眠障害とは?
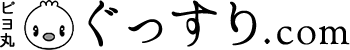
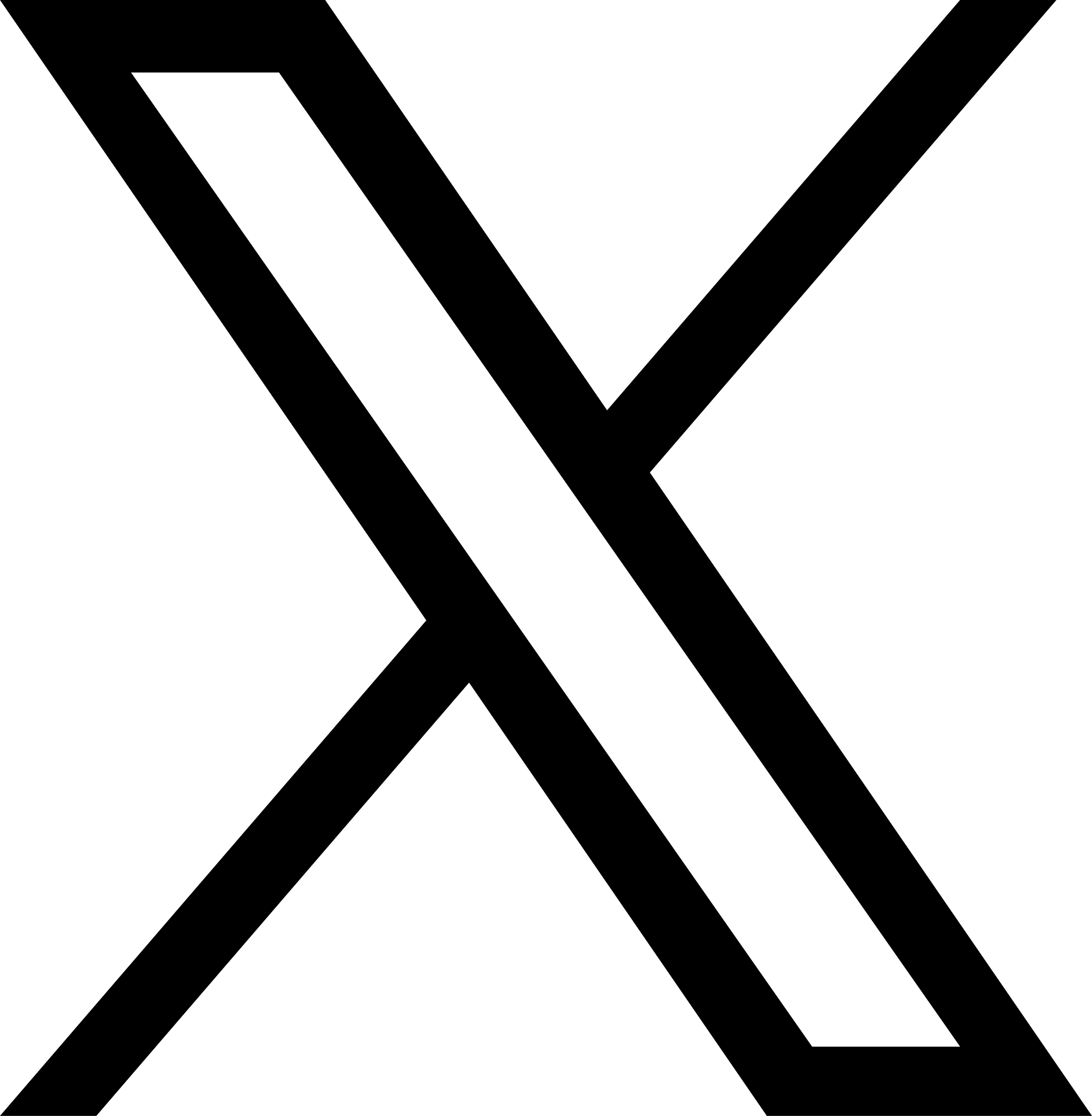




 【食後10分間エクササイズ】血糖値の上昇を抑えて老化防止
【食後10分間エクササイズ】血糖値の上昇を抑えて老化防止