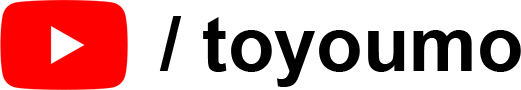眠りなサイエンス
睡眠博士ねねNene
vol. 8いびきが起きる原因と解消法
前回に引き続き、今回も読者の方からの眠りに関するご質問にお答えしていきます。
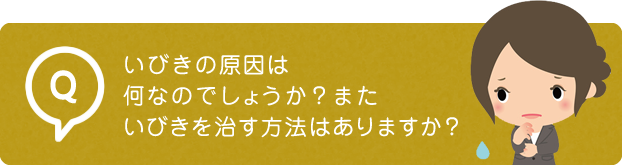
 肥満、扁桃腺肥大、飲酒…
肥満、扁桃腺肥大、飲酒…
いびきの原因はさまざま
 まずはいびきのメカニズムについてお話しましょう。いびきを引き起こす原因の代表として、肥満、扁桃腺やアデノイド(咽頭扁桃とも言う、鼻とのどの間にあるリンパ組織)の肥大、鼻中隔湾曲症(鼻の左右の仕切りの軟骨の湾曲)、下顎の小ささ、飲酒、喫煙がありますが、加えて口の周りの筋肉の衰えも一因と言われています。 仰向けで眠ることで重力によって舌の付け根(舌根)がのどの方に落ち込んだり、首周りが脂肪によって圧迫されたりすると、気道が狭まり、吸気が通る度にのど周辺が振動して雑音が起きます。これがいびきです。
まずはいびきのメカニズムについてお話しましょう。いびきを引き起こす原因の代表として、肥満、扁桃腺やアデノイド(咽頭扁桃とも言う、鼻とのどの間にあるリンパ組織)の肥大、鼻中隔湾曲症(鼻の左右の仕切りの軟骨の湾曲)、下顎の小ささ、飲酒、喫煙がありますが、加えて口の周りの筋肉の衰えも一因と言われています。 仰向けで眠ることで重力によって舌の付け根(舌根)がのどの方に落ち込んだり、首周りが脂肪によって圧迫されたりすると、気道が狭まり、吸気が通る度にのど周辺が振動して雑音が起きます。これがいびきです。
普段あまりいびきをかかない人でも、お酒を飲んだ後はいびきをかくことがあります。これは飲酒によってのど周辺の筋肉が緩んで、舌根などが落ち込みやすくなるためです。また睡眠薬も種類によって筋弛緩作用があることから、お酒と同様にいびきの原因になるとも言われています。
 口の筋肉の低下や口呼吸にも注意
口の筋肉の低下や口呼吸にも注意
 顔にはたくさんの筋肉がありますが、口の周りにある筋肉が衰えると、口をきちんと閉じていられずに、睡眠時だけでなく日中もポカンと口を開けた状態になってしまうことがあります。唇と舌は動きが連動していて、口を開けたまま眠るとつられて舌も落ち込みやすくなるそうです。つまり睡眠中も口を閉じていられる筋力をつけることも、いびきの改善と防止のカギと言えるのです。
顔にはたくさんの筋肉がありますが、口の周りにある筋肉が衰えると、口をきちんと閉じていられずに、睡眠時だけでなく日中もポカンと口を開けた状態になってしまうことがあります。唇と舌は動きが連動していて、口を開けたまま眠るとつられて舌も落ち込みやすくなるそうです。つまり睡眠中も口を閉じていられる筋力をつけることも、いびきの改善と防止のカギと言えるのです。
またいびきをかく人の多くは口呼吸をしています。鼻呼吸の場合は、鼻毛や鼻の分泌物によって、空気中の雑菌などがある程度除去されますが、口呼吸ではそれができないばかりか、のどの粘膜を乾燥させてしまいます。のどが炎症を起こして腫れ、さらに気道を狭めるという悪循環になりかねません。口呼吸は、感染症にかかりやすいなど、いびき以外のデメリットもあるので、鼻呼吸の習慣をつけましょう。鼻炎などで鼻呼吸が難しい人は、まずはそちらの治療が先かもしれませんね。
 酸素の供給が減ると重大な病気にも
酸素の供給が減ると重大な病気にも
 一時的ないびきや寝始めの頃だけに起きるようないびきであれば、さほど心配する必要はありません。しかし、気道が完全にふさがれて肺に空気を送れなくなる無呼吸が発生している場合は、睡眠時無呼吸症候群(SAS)の可能性があります。また無呼吸ではなくても、気道が狭まって必要な酸素量が確保できなくなると、血圧が上昇して脳に酸素が供給されなくなり、高血圧や脳梗塞、脳障害、脳卒中といった重篤な病気を引き起こす危険性も高まります。大きないびきを一晩中かいているようであれば、一度専門医に相談されることをおすすめします。
一時的ないびきや寝始めの頃だけに起きるようないびきであれば、さほど心配する必要はありません。しかし、気道が完全にふさがれて肺に空気を送れなくなる無呼吸が発生している場合は、睡眠時無呼吸症候群(SAS)の可能性があります。また無呼吸ではなくても、気道が狭まって必要な酸素量が確保できなくなると、血圧が上昇して脳に酸素が供給されなくなり、高血圧や脳梗塞、脳障害、脳卒中といった重篤な病気を引き起こす危険性も高まります。大きないびきを一晩中かいているようであれば、一度専門医に相談されることをおすすめします。
ご自身のいびきは気づきにくいと思いますが、十分な睡眠時間を取っているのに目覚めがすっきりしない、日中に強い眠気が起きるといった症状のある方は、注意が必要です。
 成長に影響を及ぼす子どものいびき
成長に影響を及ぼす子どものいびき
 大人だけでなく子どももいびきをかきます。中にはSASと診断されるケースもあります。原因としては、扁桃腺やアデノイドの肥大によるものが多い傾向ですが、近年は、肥満やあごが小さいといったことによるいびきが見られるようになっています。
大人だけでなく子どももいびきをかきます。中にはSASと診断されるケースもあります。原因としては、扁桃腺やアデノイドの肥大によるものが多い傾向ですが、近年は、肥満やあごが小さいといったことによるいびきが見られるようになっています。
成長期の子どもにとって、睡眠中の酸素の供給が減ることは発達障害を引き起こす可能性があります。しかし、親が子どものいびきを重要視しないで放置していることも多いようです。ひとつの目安として、お子さんがいびきをかいていたら、胸を観察してみてください。呼吸に合わせて胸が凹んでいたら、狭くなった気道を無理に吸気が通ろうとするあまり、胸郭が変形したとも考えられます。速やかに病院に行きましょう。
 いびきの程度に合わせた対策を
いびきの程度に合わせた対策を
 軽いいびきなら、枕を低くしたり横向きに寝たりといった簡単な工夫で改善することがありますが、まずは、肥満の人は減量を、喫煙者は禁煙を、そしてお酒の量を減らすなどの対策が挙げられます。口周りの筋力をつけるには、トレーニンググッズがいろいろと発売されているので、取り入れてみるのもいいと思います。
軽いいびきなら、枕を低くしたり横向きに寝たりといった簡単な工夫で改善することがありますが、まずは、肥満の人は減量を、喫煙者は禁煙を、そしてお酒の量を減らすなどの対策が挙げられます。口周りの筋力をつけるには、トレーニンググッズがいろいろと発売されているので、取り入れてみるのもいいと思います。
扁桃腺肥大や鼻中隔湾曲症は、手術で症状を治すことでいびきも改善されることがあります。さらにマウスピースを使って下顎を前に出して気道を開く方法や、SASの人にはCPAP(シーパップ)という鼻にマスクをつけて眠る方法などがありますが、これらは医師の指導のもとに行います。ご自身の状態に合わせた改善策を検討してください。
たかがいびき、されどいびき。いびきは自分では把握できないものです。ご家族や一緒にお住まいの方が気に かけて、心配な点がある時は医師に相談することをおすすめします。いびきは睡眠の質を低下させ、日中のパフォーマンスに影響を及ぼすばかりか、重度になると命にかかわる状態にもなります。放置せずに対策を取りましょう。
 vol. 1寝つきの悪さの原因と対策
vol. 1寝つきの悪さの原因と対策 vol. 2食生活と眠りの関係
vol. 2食生活と眠りの関係 vol. 3短期的な睡眠不足を乗り切る裏ワザ
vol. 3短期的な睡眠不足を乗り切る裏ワザ vol. 4睡眠不足が脳と体の成長に与える影響について
vol. 4睡眠不足が脳と体の成長に与える影響について vol. 5睡眠で分かるカラダ不調のサイン
vol. 5睡眠で分かるカラダ不調のサイン vol. 6欧米と日本の睡眠習慣の違い
vol. 6欧米と日本の睡眠習慣の違い vol. 7寝つきと寝起きのひと工夫
vol. 7寝つきと寝起きのひと工夫 vol. 8いびきが起きる原因と解消法
vol. 8いびきが起きる原因と解消法 vol. 9寝坊の原因と解消法
vol. 9寝坊の原因と解消法 vol. 10赤ちゃんとお子さんのより良い睡眠のために
vol. 10赤ちゃんとお子さんのより良い睡眠のために vol. 11目覚めに体がイタイのはこんな理由かも?
vol. 11目覚めに体がイタイのはこんな理由かも? vol. 12良い目覚めと悪い目覚めの違い
vol. 12良い目覚めと悪い目覚めの違い vol. 13仮眠や昼寝を効率よく取るコツ
vol. 13仮眠や昼寝を効率よく取るコツ vol. 14睡眠不足のリスク
vol. 14睡眠不足のリスク vol. 15健康習慣をおさらいしよう!
vol. 15健康習慣をおさらいしよう! vol. 16睡眠障害とは?
vol. 16睡眠障害とは?
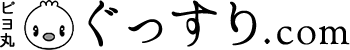
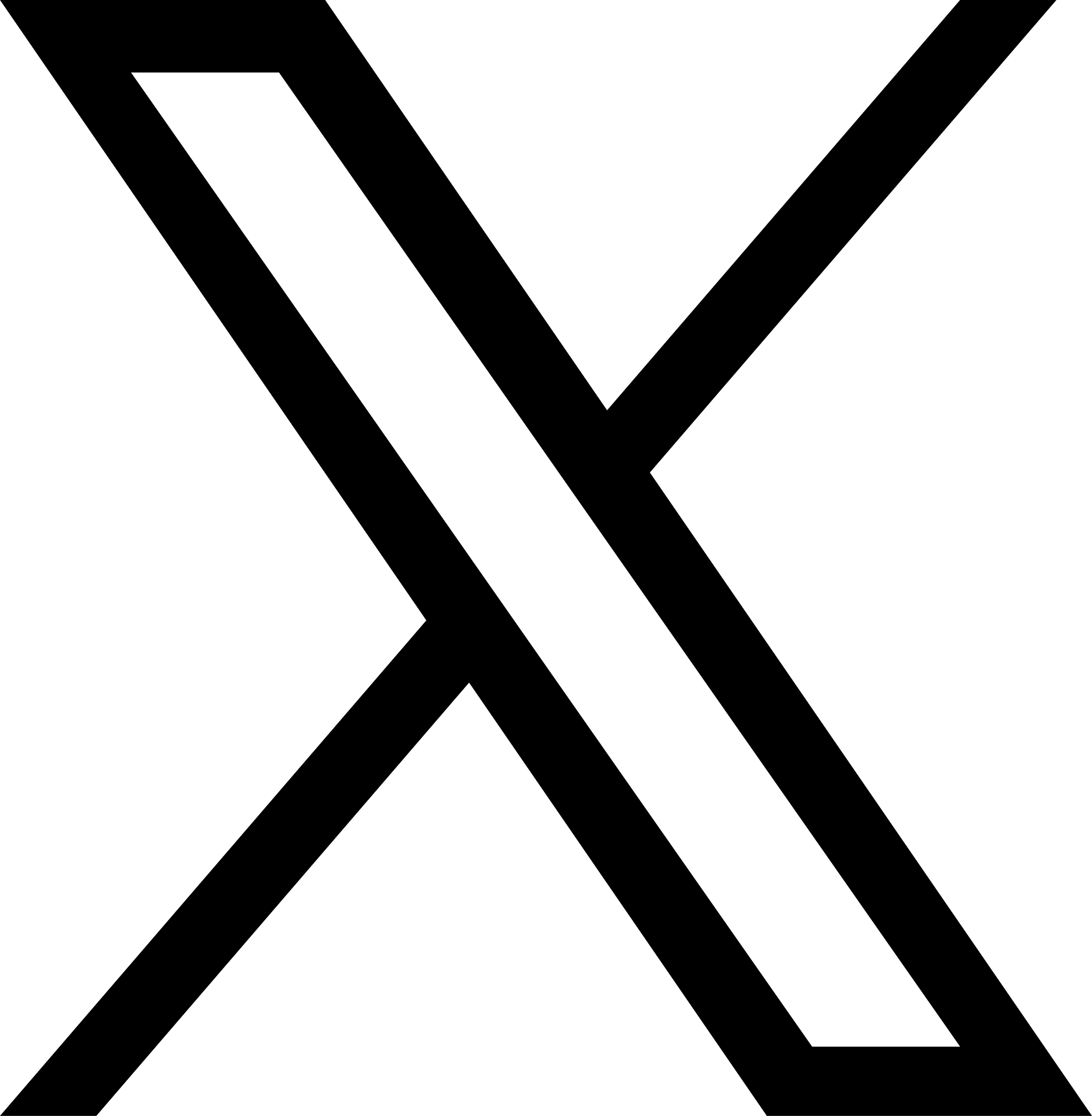




 【食後10分間エクササイズ】血糖値の上昇を抑えて老化防止
【食後10分間エクササイズ】血糖値の上昇を抑えて老化防止