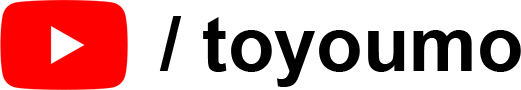眠りなサイエンス
睡眠博士ねねNene
vol. 9寝坊の原因と解消法
今回も読者の方からの眠りに関するご質問にお答えしていきます。
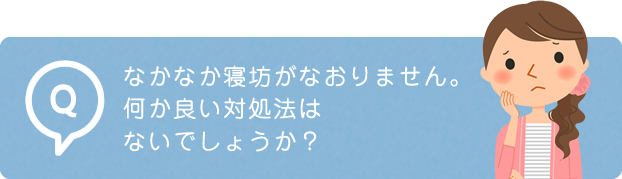
 まずは起きる時刻を一定にする
まずは起きる時刻を一定にする
 年齢にかかわりなく朝が苦手という話をよく耳にします。ついついテレビゲームに熱中したり深夜番組を見たりして就寝時刻が遅くなると、当然、朝起きるのが辛くなりますね。こうした日々の生活習慣だけでなく、例えば年末年始の休暇や夏休みの間に夜更かしを続けただけでも、昼夜逆転の生活から戻せなくなってしまうことがあります。場合によっては、体内時計がうまく働かない「概日リズム睡眠障害」になり、治療が必要になるケースもあります。
年齢にかかわりなく朝が苦手という話をよく耳にします。ついついテレビゲームに熱中したり深夜番組を見たりして就寝時刻が遅くなると、当然、朝起きるのが辛くなりますね。こうした日々の生活習慣だけでなく、例えば年末年始の休暇や夏休みの間に夜更かしを続けただけでも、昼夜逆転の生活から戻せなくなってしまうことがあります。場合によっては、体内時計がうまく働かない「概日リズム睡眠障害」になり、治療が必要になるケースもあります。
予防策として、まずは起床時刻を一定にすることです。学校や仕事が休みだからと、昼頃までダラダラと寝ているのは睡眠サイクルを乱す原因になります。休日でも、平日との起床時刻の差を1時間以内に抑えることを心がけてみてください。
 目覚めたらカーテンを開けて、朝日をしっかり浴びよう!
目覚めたらカーテンを開けて、朝日をしっかり浴びよう!
 体内時計の1日は、24時間よりも少し長いのですが、朝日を浴びることでその誤差がリセットされ、身体は新たな1日をスタートできるのです。目覚めた後、しっかり朝日を浴びて身体に「朝」を認知させることで、その約14時間~16時間後に体内でメラトニンが分泌され始め、そのさらに1~2時間後に眠気がやってきます。
体内時計の1日は、24時間よりも少し長いのですが、朝日を浴びることでその誤差がリセットされ、身体は新たな1日をスタートできるのです。目覚めた後、しっかり朝日を浴びて身体に「朝」を認知させることで、その約14時間~16時間後に体内でメラトニンが分泌され始め、そのさらに1~2時間後に眠気がやってきます。
メラトニンは、睡眠ホルモンとも呼ばれる、睡眠をコントロールする物質です。朝の行動が、夜に眠気を起こすカギであり、夜にきちんと眠くなることが、翌朝のスッキリとした目覚めにつながるわけです。
 光による睡眠不足に注意
光による睡眠不足に注意
 メラトニンの分泌は、日が落ちる夕方から夜にかけて増えていきます。しかし、夜に強い光を見ると分泌が抑制されて眠気が起きにくくなってしまうのです。夜間は間接照明を使うなど、なるべく室内の明かりを抑えることをおすすめします。特にお子さんは光の感受性が高いので、照明には気を配りましょう。
メラトニンの分泌は、日が落ちる夕方から夜にかけて増えていきます。しかし、夜に強い光を見ると分泌が抑制されて眠気が起きにくくなってしまうのです。夜間は間接照明を使うなど、なるべく室内の明かりを抑えることをおすすめします。特にお子さんは光の感受性が高いので、照明には気を配りましょう。
お子さんに限らず、寝る直前までパソコンやスマートフォンを使うことも、画面の光が脳を目覚めさせてしまうのでNGです。
 睡眠時間を削っても仕事や勉強ははかどらない!
睡眠時間を削っても仕事や勉強ははかどらない!
 ワシントン州立大学のハンス・ヴァン・ドンゲン教授が、2003年に行った実験をご紹介しましょう。健康な成人48人を3つのグループに分け、それぞれ8時間睡眠/6時間睡眠/4時間睡眠を2週間続けてもらいました。その後、反応速度を測定したところ、反応が遅れた回数の平均が、8時間睡眠のグループは3回、6時間睡眠は10回、4時間睡眠は15回だったのです。睡眠時間が短くなるほどに、反応速度が下がることが分かりました。
ワシントン州立大学のハンス・ヴァン・ドンゲン教授が、2003年に行った実験をご紹介しましょう。健康な成人48人を3つのグループに分け、それぞれ8時間睡眠/6時間睡眠/4時間睡眠を2週間続けてもらいました。その後、反応速度を測定したところ、反応が遅れた回数の平均が、8時間睡眠のグループは3回、6時間睡眠は10回、4時間睡眠は15回だったのです。睡眠時間が短くなるほどに、反応速度が下がることが分かりました。
ここで注目してほしいのは、6時間睡眠の人たちが、認知能力の低下を自覚していなかった点です。実際にはパフォーマンスが落ちているのに、自分ではできていると思っていました。6時間も眠れば睡眠不足とは感じないかもしれませんが、実は行動に大きな障害が生じることがあるのです。
睡眠時間が減ると、記憶の整理や定着を行うレム睡眠が短くなってしまいます。すると、学んだことが脳に記録されず、せっかくの勉強や経験が無駄になりかねません。寝坊の一番の解決方法は、やはり適度な睡眠時間をとることです。毎日夜更かしをしているなど、明らかな睡眠不足による寝坊の場合、生活パターンを見直して根本的な解決を図ることが大切です。
 vol. 1寝つきの悪さの原因と対策
vol. 1寝つきの悪さの原因と対策 vol. 2食生活と眠りの関係
vol. 2食生活と眠りの関係 vol. 3短期的な睡眠不足を乗り切る裏ワザ
vol. 3短期的な睡眠不足を乗り切る裏ワザ vol. 4睡眠不足が脳と体の成長に与える影響について
vol. 4睡眠不足が脳と体の成長に与える影響について vol. 5睡眠で分かるカラダ不調のサイン
vol. 5睡眠で分かるカラダ不調のサイン vol. 6欧米と日本の睡眠習慣の違い
vol. 6欧米と日本の睡眠習慣の違い vol. 7寝つきと寝起きのひと工夫
vol. 7寝つきと寝起きのひと工夫 vol. 8いびきが起きる原因と解消法
vol. 8いびきが起きる原因と解消法 vol. 9寝坊の原因と解消法
vol. 9寝坊の原因と解消法 vol. 10赤ちゃんとお子さんのより良い睡眠のために
vol. 10赤ちゃんとお子さんのより良い睡眠のために vol. 11目覚めに体がイタイのはこんな理由かも?
vol. 11目覚めに体がイタイのはこんな理由かも? vol. 12良い目覚めと悪い目覚めの違い
vol. 12良い目覚めと悪い目覚めの違い vol. 13仮眠や昼寝を効率よく取るコツ
vol. 13仮眠や昼寝を効率よく取るコツ vol. 14睡眠不足のリスク
vol. 14睡眠不足のリスク vol. 15健康習慣をおさらいしよう!
vol. 15健康習慣をおさらいしよう! vol. 16睡眠障害とは?
vol. 16睡眠障害とは?
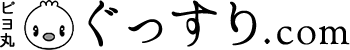
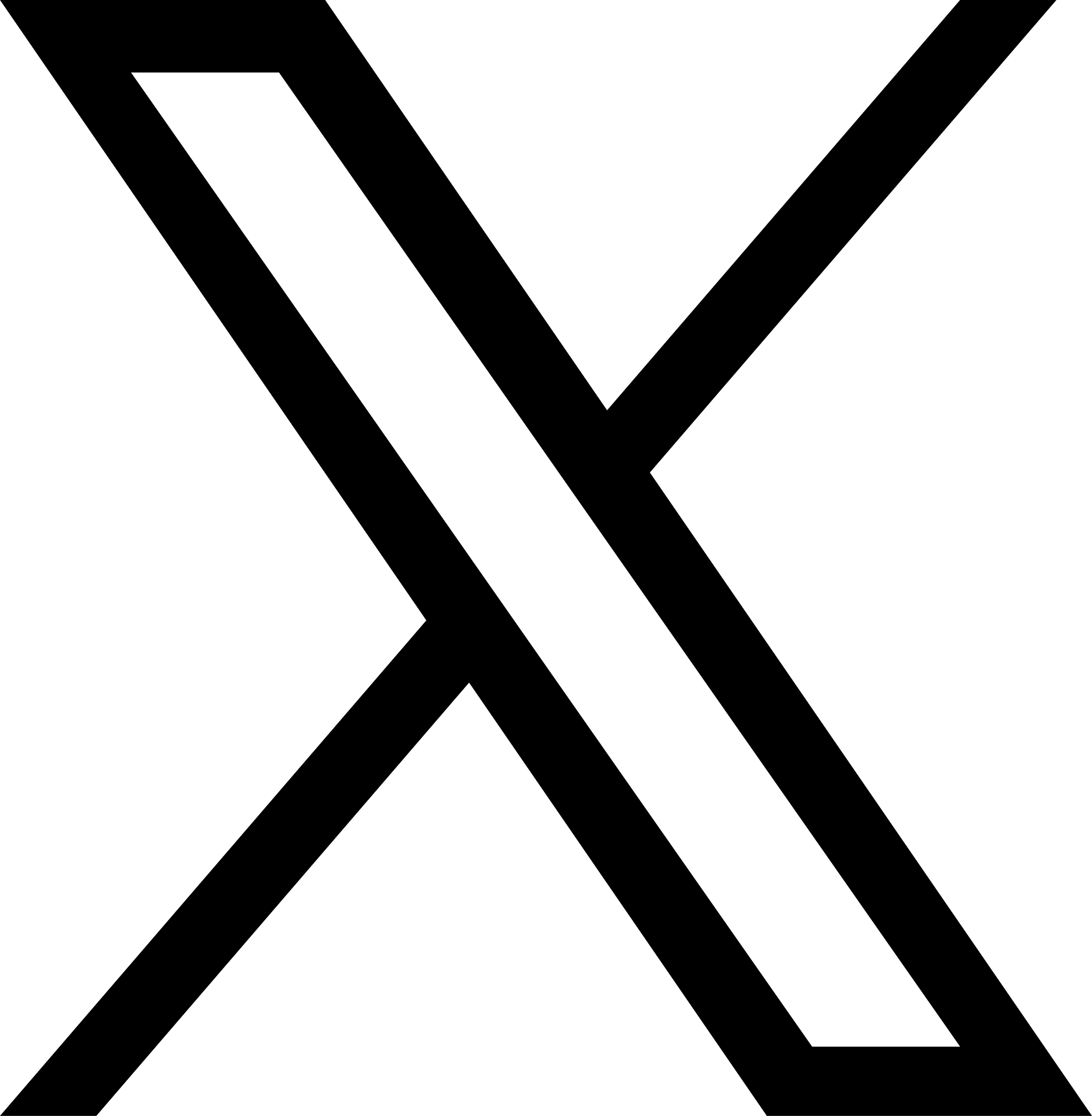




 【食後10分間エクササイズ】血糖値の上昇を抑えて老化防止
【食後10分間エクササイズ】血糖値の上昇を抑えて老化防止