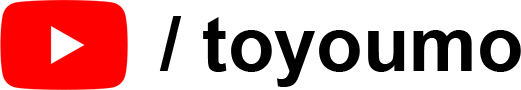コラム
美容コンサルタント美羽Miu
vol. 27睡眠不足は体温が原因? 冷えで眠れない人必見!「体温の下げ方」
「冷えで、よく眠れない」こんな悩みを抱えていませんか?
身体の冷えは、睡眠にも大きな影響を及ぼします。ただ、単に体を温めればよいというものではありません。睡眠に大切なのは、温めた体温を下げることです。
今回は、眠りの質を改善するための「体温の下げ方」について分かりやすく紹介します。
自然な眠気は、体温の低下とともに訪れる
 人間の体温は、1日の中で変動しています。個人差はありますが、午前4~5時頃が最も低く、そこからだんだん高くなっていき午後7~8時頃にピークを迎え、午後9時以降はまた徐々に低くなっていき、さらに眠り始めるとともに急速に下がります。
人間の体温は、1日の中で変動しています。個人差はありますが、午前4~5時頃が最も低く、そこからだんだん高くなっていき午後7~8時頃にピークを迎え、午後9時以降はまた徐々に低くなっていき、さらに眠り始めるとともに急速に下がります。
人の身体は、体温が下がると眠くなるようにできています。この機能がしっかり働いていれば、夜になり体温が下がっていくにつれ、自然な眠気が訪れるのです。
冷え性の人が「よく眠れない」のはなぜ?
 「体温が下がると眠くなるなら、冷え性の人は寝つきが良いはずでは?」と疑問に思ったかもしれません。実際は、冷え性の人は手や足などの末端への血流が悪く、その温度が低くなっているだけで、体温が低いわけではありません。
「体温が下がると眠くなるなら、冷え性の人は寝つきが良いはずでは?」と疑問に思ったかもしれません。実際は、冷え性の人は手や足などの末端への血流が悪く、その温度が低くなっているだけで、体温が低いわけではありません。
体温を下げるためには、身体の中にこもった熱を外へ逃がす必要があり、人の身体には皮膚から熱を放熱させる機能が備わっています。例えば赤ちゃんが眠いとき手がポカポカと温かくなるのは、そこから熱を逃がしているためです。
手足への血流が悪い冷え性の人は、体内の熱を放熱しにくい状態と言えます。冷え性の人が「あまり寝つけない、よく眠れない」といった悩みを抱えやすいのは、放熱により体温を下げる機能が弱まっているためです。
眠りに大切な深部体温とは
深部体温は、内臓など体内部の温度の事で、1日周期のリズムで上下に変動するものです。
一般的に、日中は深部体温が高く、覚醒レベルも高まる傾向にあります。夜になると深部体温は下がり始め、それによって眠気が生じるのです。
睡眠中の深部体温はそのまま低下し、特に午前4~5時頃が最も低く、午後7~8時頃が最も深部体温が高まります。深部体温が下がる理由は、手足への血流が良くなることで身体の深部にある熱が手や足に運ばれ、そこから放出されるためです。
深部体温の下げ方
深部体温を下げるには、夜に湯船に浸かり体を温めることが効果的といわれています。ぬるめのお湯に浸かることで深部体温が少し上昇します。上昇した深部体温を下げようと血流がよくなり、放熱を促進してくれます。
また、身体には1日のリズムがあり、夜には深部体温が下がる機能が備わっています。入浴によって手足への血流が増加することで、深部体温を下げるスピードが速くなるのです。
体温と外気温の関係
自律神経の働きにより、外気温の変化に対しても体温は一定に保たれます。
そのため、深部体温を下げる目的で部屋の温度を低くして寒さを感じると、血管を縮めて血液をあまり流さないようにして、体内の熱を外へ逃がしにくくします。さらに寒さを感じると、体は熱を発生させようと震える反応を示します。結果として、深部体温はあまり変化しない上に交感神経が優位になるため、寝つきが悪くなってしまうのです。
自律神経と睡眠の関係
自律神経には、昼は脳や身体を活発に働かせる交感神経が優位になり、夜は脳や身体を休める副交感神経にする役目があります。
強いストレスを感じると交感神経が優位になり、寝つきが悪くなったり、睡眠の質が下がったりしてしまうのです。結果、睡眠不足となり、脳の機能が低下しストレスの対処能力が低くなる、という悪循環が発生してしまいます。
ストレスや睡眠不足につなげないためにも、昼は活発に活動し夜に休息・睡眠をしっかりとることを心がけ、自律神経の働きを良くするようにしましょう。
眠りを楽しむための「体温の下げ方」3つ
寝つきを良くしてぐっすり眠るために、就寝前に体温が下がりやすくなる工夫をしておきましょう。おすすめの方法を3つ紹介します。
1.ゆっくり入浴する
 お風呂は、就寝する90~30分前までの入浴を意識するとよいです。
お風呂は、就寝する90~30分前までの入浴を意識するとよいです。
布団に入る1時間前までに、38~41℃くらいのお湯にゆっくり10分ほど浸かって、深部体温をいったん上げましょう。少し汗ばむくらいでお風呂を出るとちょうどよく、そこから深部体温が下がるにつれて自然な眠気が訪れます。
なるべく就寝30分前には入浴を済ませ、リラックスした状態を作っておきましょう。
ここで気を付けて欲しいことは、お湯の温度です。熱すぎる温度で入浴してしまうと、逆効果になる可能性があります。熱いお湯に浸かりたいのであれば、より早い時刻に入浴した方がよいでしょう。
2.食べ物で内側から温める
 夕食には身体を温めてくれる食材を積極的に取り入れ、内側からも対策をしていきましょう。ショウガや唐辛子の他、寒い時期に旬を迎える根菜(かぼちゃ、ごぼう、にんじんなど)もおすすめです。
夕食には身体を温めてくれる食材を積極的に取り入れ、内側からも対策をしていきましょう。ショウガや唐辛子の他、寒い時期に旬を迎える根菜(かぼちゃ、ごぼう、にんじんなど)もおすすめです。
また、ゆず茶や生姜湯などの、60℃~70℃前後の暖まる温度の飲み物で深部体温を高めると、入眠時に深部体温を下げる効果が期待できます。
ゆず茶は、ゆずジャムをお湯で割るだけなので、手間がかからずおすすめです。
ただし、寝る直前に食べ物や飲み物で体を温めてしまうと、深部体温が高い状態で眠ることになるので避けましょう。食事は就寝の3時間前までに済ませ、胃腸が活発に活動している状態で入眠しないようにしましょう。
3.リラックスする
 軽めのストレッチやアロマの香りを楽しむ、部屋着からパジャマに着替えるなど就寝前はリラックスしましょう。副交感神経が優位になって血流が良くなり、手足など身体の末端から熱を逃がして体温が下がります。
軽めのストレッチやアロマの香りを楽しむ、部屋着からパジャマに着替えるなど就寝前はリラックスしましょう。副交感神経が優位になって血流が良くなり、手足など身体の末端から熱を逃がして体温が下がります。
具体的なリラックス方法としては、PCやスマホ、ゲームなどは寝る1時間前から控えたり、照明を暗めの暖色系にしたりすることがおすすめです。
ほかにも、就寝30分前にストレッチをして呼吸を整えることや、就寝前~就寝中にアロマやお香などの香りをかぐことも効果的なリラックス方法です。
良い眠りの邪魔をする「行動」とは?
 ここで注意したいのが、体温を上げようとするあまり「目が冴える行動」をしてしまうことです。
ここで注意したいのが、体温を上げようとするあまり「目が冴える行動」をしてしまうことです。
たとえば、42℃以上の熱いお湯に浸かったり、激しい運動をしてしまったり……。こうした行動は覚醒・興奮を司る交感神経を優位にしてしまうため、よけいに眠れなくなってしまいます。
ここでは、注意するべき3つの行動について詳しくお伝えします。
1.靴下を履いたまま寝ない
靴下を履いたまま寝ないようにしましょう。靴下が足からの放熱を妨げてしまい、かえって、眠りの質が下がったりしてしまいます。足元の冷えが気になるときは、レッグウォーマーなどを着けて、靴下は脱いで眠るようにしましょう。
2.寝る前の飲酒はNG
寝るための飲酒はおすすめできません。アルコールには睡眠の質を下げてしまう働きがある上、利尿作用により夜中に目覚めやすくなります。依存症のリスクもあるため、寝酒の習慣はできるだけ避けたほうが良いでしょう。
また、深部体温を下げるために、冷たい飲み物を摂るのも控えましょう。冷たい飲み物を摂ってしまうと、外気温と同様に交感神経が優位になり、結果として眠れなくなることがあります。
カフェイン入りの飲料は、カフェインに覚醒作用があり、コーヒー1杯で3~4時間続くこともありますので、夕方以降は控えましょう。
3.寝る前の物理的・精神的ストレスを避ける
体を温めようと就寝直前にお風呂で熱いお湯に浸かることや、激しい運動をすること、就寝直前までPCやスマホ、ゲームなどすることは交感神経が優位になります。
そのほか、心配事や考え事もストレスにつながりますので、それらは起きてから考えるようにしてベッドに持ち込まないよう意識することも大切です。
以上のことに気を付け、質の良い睡眠を目指しましょう。
- vol. 1美肌をつくる睡眠のコツ。肌と眠りの深い関係とは?
- vol. 2本当に髪に良いシャンプーのポイント3つ。日々のお手入れで艶々ヘアを目指そう!
- vol. 3ぐっすり眠れる「寝室づくり」の秘訣とは?スグできるコツを教えます
- vol. 4食事が眠りの質を変える?ぐっすり眠るための「食べ物・飲み物」上手な摂り方
- vol. 5あなたに最適な「睡眠時間」とは?ベストな睡眠時間の調べ方を教えます
- vol. 6寝苦しいのは「寝床内環境」のせいかも?ふとんの中の温度・湿度を快適に整える4つのポイント
- vol. 7寝落ちは立派な危険信号!睡眠負債のセルフチェックと解消法
- vol. 8若いあなたも注意が必要!認知症リスクを上げる危険な眠り方とは?
- vol. 9美容と健康に欠かせない!成長ホルモンの働きと、分泌を促すコツ
- vol. 10体内時計は2種類あるって知ってた?それぞれを整えて眠りの悩みを解消する3つのコツ
- vol. 11幸せホルモン・セロトニンを分泌させるコツとは?
- vol. 12もう怖くない!「金縛り」の科学的なメカニズムと予防法を解説します
- vol. 13夜はスマホを置いてリラックス♪“なかなか眠れない”を防ぐ簡単なおすすめ習慣
- vol. 14熱すぎるお湯はNG!快眠のための「正しいお風呂の入り方」
- vol. 15寝起きの肩こりの原因は?
- vol. 16夜ふかし続き、徹夜明け…眠気を覚まして仕事を乗り切る6つのコツ
- vol. 17コーヒー以外も要注意!寝付きを邪魔する「カフェイン」を含む飲み物リスト
- vol. 18寝付きのよさと間違えやすい「バタンキュー型睡眠不足」とは?予防・改善する3つのコツ
- vol. 19睡眠の質を高める「朝の過ごし方」とは?すぐ真似できる3つのポイント
- vol. 20寝付けない夜に試したいこと
- vol. 21眠り上手は痩せ上手。睡眠とダイエットの深い関係
- vol. 22日中の居眠りは病気のサイン?職場&テレワークで眠気を乗り切るコツ
- vol. 23掛け布団を選ぶ4つのコツ。眠りの質を下げないポイントは?
- vol. 24目覚めスッキリ♪ 朝に効く「香り」と簡単アロマ活用法
- vol. 25心地よく眠れる♪睡眠の質を上げる「寝具のお手入れ」のコツ
- vol. 26テレワークは睡眠不足になりやすい?リズムを崩さない4つのコツ
- vol. 27睡眠不足は体温が原因? 冷えで眠れない人必見!「体温の下げ方」
- vol. 28パワーナップで午後の仕事もサクサク♪短い仮眠の実践法と3つのポイント
- vol. 29社会的時差ボケってどんなもの?休日の寝溜めが招く意外な悪影響とは
- vol. 30寝る直前に運動してはいけないって本当?眠りと運動の関係
- vol. 31スマホ不眠を防ぐ上手な使い方とは?快眠のためのポイント5つ
- vol. 32まさに「寝る子は育つ」。子どもの睡眠を守る5つのポイント
- vol. 33睡眠の質を落とす「NG生活習慣」とは?よく眠るための簡単セルフチェック
- vol. 34快眠のカギは寝室・寝具にあり。睡眠の質をUPする「睡眠環境」を整えよう
- vol. 35ロングスリーパー、ショートスリーパーの目安は?睡眠障害との見分け方も解説
- vol. 36「よく動く人」はよく眠る♪快眠のための運動で意識したい2つのポイント
- vol. 37【寝酒はNG】睡眠の質を下げない「アルコールとの上手な付き合い方」を解説
- vol. 38春夏秋冬で変わる睡眠の特徴とは?季節ごとの快眠のコツを解説
- vol. 39夜ぐっすり、朝スッキリ♪睡眠の質を上げる日光浴のコツ
- vol. 40快眠への第一歩!質の良い眠りを手に入れるための就寝前ルーティン
- vol. 41放置は危険。「睡眠負債」が引き起こす5つのリスクと対策のポイント
- vol. 42高齢者にとっての快眠術とは?睡眠の質を高める5つのポイント
- vol. 43交替制勤務(シフトワーク)でも健康を守る睡眠マネジメント法
- vol. 44寝ても疲れがとれない人必見!見落としがちな睡眠の質を下げる4つの生活習慣と改善策
- vol. 45「週末の夜ふかしにさようなら」睡眠リズムを無理なく整えるポイント
- vol. 46昼寝と夜の睡眠はどう違う?「分割睡眠」の特徴とリスクを解説
- vol. 47ひどい「いびき」は何故起きる?生活にひそむ意外な原因をチェック
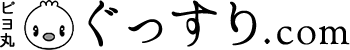
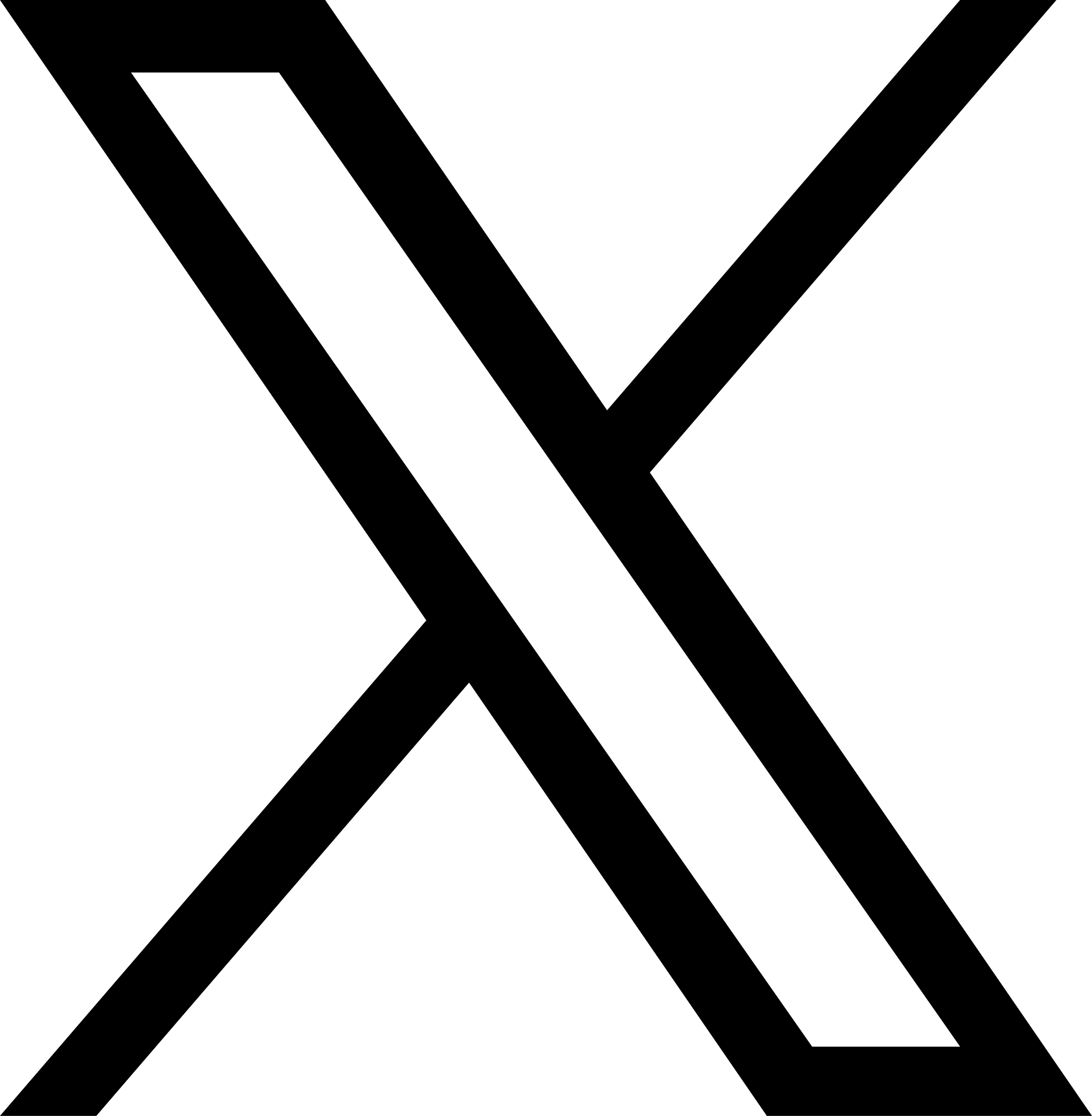




 ピヨ丸まちがいさがし(2026年1月)
ピヨ丸まちがいさがし(2026年1月)