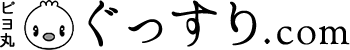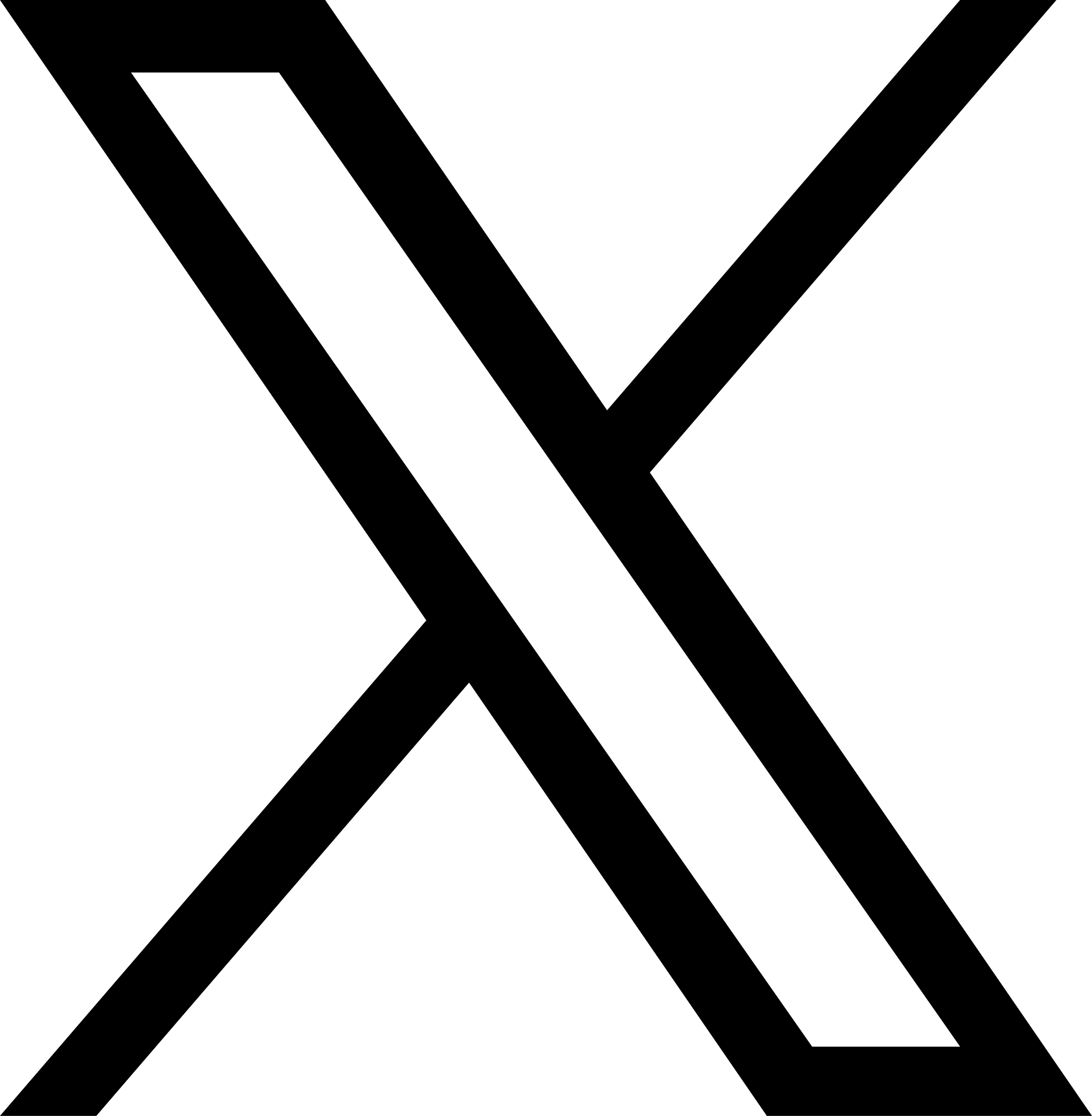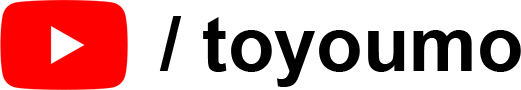コラム
美容コンサルタント美羽Miu
vol. 47ひどい「いびき」は何故起きる?生活にひそむ意外な原因をチェック
「最近、ひどい”いびき”をかいているよ」と家族に言われて、ドキッとした経験はありませんか? 眠っている間に無意識にかいている、いびき。本人にとっては気づきにくいものですが、いびきを放置することによって睡眠の質が下がり、日中の集中力低下や強い眠気など身体の不調につながることもあるため、注意が必要です。 いびきは、空気の通り道(気道)が狭くなることで起こります。今回は、いびきを悪化させる要因と、今日から始められる対策を分かりやすく解説しましょう。
「いびき」は、睡眠中の呼吸が滞っている注意信号
 夜中に自分のいびきで目が覚めたり、家族に「最近いびきが大きいね」と言われたりしたことはありませんか?
いびきとは、眠っているときに喉や鼻の奥にある空気の通り道(上気道)が狭くなり、そこを空気が通ることで、周辺の組織が振動して生じる呼吸音の一種です。起きている間は筋肉がしっかりと気道を支えていますが、眠ると筋肉がゆるむため、音が生じやすくなります。
夜中に自分のいびきで目が覚めたり、家族に「最近いびきが大きいね」と言われたりしたことはありませんか?
いびきとは、眠っているときに喉や鼻の奥にある空気の通り道(上気道)が狭くなり、そこを空気が通ることで、周辺の組織が振動して生じる呼吸音の一種です。起きている間は筋肉がしっかりと気道を支えていますが、眠ると筋肉がゆるむため、音が生じやすくなります。
疲れている日やお酒を飲んだ夜などに一時的にいびきが出ることがありますが、毎晩のように続く「習慣的ないびき」が出ている場合は、睡眠中の呼吸がスムーズにできていない可能性があります。呼吸がしっかりできていないと眠りが浅くなり、朝すっきり起きられなかったり、日中に強い眠気を感じたりすることがあります。
つまり、いびきは「しっかり眠れていない」注意信号。自分では気づきにくいからこそ、家族やパートナーからの指摘をきっかけに、生活習慣や寝室環境を見直してみることが大切です。
「いびき」を悪化させやすい生活習慣と環境
いびきは、顎の大きさなどの骨格や鼻づまり、アレルギー、肥満といった身体的な要因で起こりやすくなりますが、生活習慣や寝室の環境によって悪化することがあります。ここでは、いびきを強めてしまう要因について見ていきましょう。
飲酒・喫煙
お酒を飲むと、アルコールの作用で筋肉がゆるみます。喉周りの筋肉がゆるむと、舌のつけ根が喉の奥に落ち込み、空気の通り道が狭くなり、いびきが強まることがあります。 また喫煙(加熱式タバコを含む)は、鼻や喉の粘膜を刺激して炎症やむくみを引き起こします。すると鼻呼吸がしづらくなり、口呼吸になって、いびきが生じやすくなります。 習慣的ないびきが気になる場合は、量を減らしたり、寝る前は控えたり、無理のない範囲で工夫してみましょう。
疲労・睡眠不足
疲労や睡眠不足も、いびきを悪化させる要因です。疲れが溜まっていると、喉や舌を支える筋肉が緩みやすくなり、舌のつけ根が喉の奥に落ち込みやすくなります。その結果、空気の通り道が狭くなり、いびきが強まります。 また、睡眠不足が続くと、深い眠りが増え、筋肉がいっそう緩くなりやすくなります。すると、気道が塞がっていびきが増え、いびきによって睡眠の質が下がり、さらに睡眠不足の状態へ……という悪循環を招きやすいため、注意が必要です。
寝姿勢
仰向けの姿勢で眠ると、重力の影響で舌が落ち込みやすく、いびきにつながる場合があります。そのため、横向きで眠ることでいびきが軽くなる人もいます。ただし、普段仰向けで眠る方が無理に横向きを続けると、かえって眠りが浅くなることがあります。姿勢は無理に変える必要はなく、呼吸がしやすく、自然に眠れる体勢を基本としましょう。
寝室の状態
寝室が乾燥していると、鼻の粘膜が刺激されて炎症を起こし、気道が圧迫されていびきが生じやすくなります。エアコンの暖房を強くしすぎず、必要に応じて加湿器を使うなど乾燥しすぎないようにしましょう。 一方、日中も含めて湿度が高い状態が続いていると、カビやダニなどのアレルゲンが増え、鼻炎を悪化させることがあります。日中はしっかり換気や掃除をおこないましょう。
今日からできる!「いびき」を改善するポイント
生活習慣を整えることが、最大の予防策
いびきを軽くするための第一歩は、生活習慣の見直しです。アルコールやタバコはいびきを悪化させる原因になるため、量やタイミングを変えて、就寝直前は控えるようにしましょう。 さらに、睡眠不足や疲労が続くと、筋肉が過度に緩んでいびきが強まることがあります。毎日しっかりと睡眠時間を確保し、起床・就寝リズムを一定に維持することが大切です。
寝室環境と姿勢を整え、呼吸しやすい眠りへ
寝姿勢と環境を整えることも、いびき対策に有効です。仰向けでは舌が喉の奥に落ち込みやすいため、横向きで寝ると呼吸がしやすくなる場合があります。ただし、無理に姿勢を変えて、違和感で眠れないなら意味がありません。横向きにこだわらず自然にリラックスできる姿勢を保てるようにしましょう。 寝室の湿度にも気をつけましょう。乾燥は鼻や喉の粘膜を刺激し、鼻づまりや口呼吸につながることがあります。一方、湿度が高い状態が日中も含めて続く場合は、カビやダニなどのアレルゲンが増えやすくなり、鼻炎が悪化することがあります。季節に合わせて換気や加湿を調整し、心地よい環境を作りましょう。
軽い運動や呼吸の改善
日中の軽い運動やストレッチは姿勢を整え、呼吸がしやすい状態を保つ助けになります。また、普段から鼻呼吸を意識することで、口呼吸が減っていびきが軽くなることがあります。
それでも改善しないときは、医療機関へ相談を
 もし、「大きないびきが毎晩のように続く」「睡眠中に呼吸が止まる」といった症状が見られる場合は、「睡眠時無呼吸症候群」を発症している可能性があります。睡眠時無呼吸症候群を放置すると高血圧や心疾患、脳卒中などのリスクが高まることが知られています。
慢性的ないびきは、医療機関で原因を確認し、専門的な治療をおこなうほうが安心です。「たかがいびき」と自己判断せず、できるだけ早めに専門医を受診しましょう。
もし、「大きないびきが毎晩のように続く」「睡眠中に呼吸が止まる」といった症状が見られる場合は、「睡眠時無呼吸症候群」を発症している可能性があります。睡眠時無呼吸症候群を放置すると高血圧や心疾患、脳卒中などのリスクが高まることが知られています。
慢性的ないびきは、医療機関で原因を確認し、専門的な治療をおこなうほうが安心です。「たかがいびき」と自己判断せず、できるだけ早めに専門医を受診しましょう。
【監修】東京ベイ・浦安市川医療センター CEO / 医師 神山 潤 先生
 睡眠、特にレム睡眠を脳機能評価手段の一つとして捉える臨床的な試みに長年取り組む。
睡眠、特にレム睡眠を脳機能評価手段の一つとして捉える臨床的な試みに長年取り組む。
旭川医科大学、UCLAでは睡眠の基礎研究に従事。米国から帰国後、日本の子どもたちの睡眠事情の実態(遅寝遅起き)に衝撃を受け、社会的啓発活動を開始している。
【主な著書】
・朝起きられない人のねむり学 一日24時間の賢い使い方
・眠りは脳と心の栄養! 睡眠がよくわかる事典 早起き・早寝で元気になれる
・睡眠で人生が劇的に変わる生体時計活性法 (講談社+α新書)
他多数
- vol. 1美肌をつくる睡眠のコツ。肌と眠りの深い関係とは?
- vol. 2本当に髪に良いシャンプーのポイント3つ。日々のお手入れで艶々ヘアを目指そう!
- vol. 3ぐっすり眠れる「寝室づくり」の秘訣とは?スグできるコツを教えます
- vol. 4食事が眠りの質を変える?ぐっすり眠るための「食べ物・飲み物」上手な摂り方
- vol. 5あなたに最適な「睡眠時間」とは?ベストな睡眠時間の調べ方を教えます
- vol. 6寝苦しいのは「寝床内環境」のせいかも?ふとんの中の温度・湿度を快適に整える4つのポイント
- vol. 7寝落ちは立派な危険信号!睡眠負債のセルフチェックと解消法
- vol. 8若いあなたも注意が必要!認知症リスクを上げる危険な眠り方とは?
- vol. 9美容と健康に欠かせない!成長ホルモンの働きと、分泌を促すコツ
- vol. 10体内時計は2種類あるって知ってた?それぞれを整えて眠りの悩みを解消する3つのコツ
- vol. 11幸せホルモン・セロトニンを分泌させるコツとは?
- vol. 12もう怖くない!「金縛り」の科学的なメカニズムと予防法を解説します
- vol. 13夜はスマホを置いてリラックス♪“なかなか眠れない”を防ぐ簡単なおすすめ習慣
- vol. 14熱すぎるお湯はNG!快眠のための「正しいお風呂の入り方」
- vol. 15寝起きの肩こりの原因は?
- vol. 16夜ふかし続き、徹夜明け…眠気を覚まして仕事を乗り切る6つのコツ
- vol. 17コーヒー以外も要注意!寝付きを邪魔する「カフェイン」を含む飲み物リスト
- vol. 18寝付きのよさと間違えやすい「バタンキュー型睡眠不足」とは?予防・改善する3つのコツ
- vol. 19睡眠の質を高める「朝の過ごし方」とは?すぐ真似できる3つのポイント
- vol. 20寝付けない夜に試したいこと
- vol. 21眠り上手は痩せ上手。睡眠とダイエットの深い関係
- vol. 22日中の居眠りは病気のサイン?職場&テレワークで眠気を乗り切るコツ
- vol. 23掛け布団を選ぶ4つのコツ。眠りの質を下げないポイントは?
- vol. 24目覚めスッキリ♪ 朝に効く「香り」と簡単アロマ活用法
- vol. 25心地よく眠れる♪睡眠の質を上げる「寝具のお手入れ」のコツ
- vol. 26テレワークは睡眠不足になりやすい?リズムを崩さない4つのコツ
- vol. 27睡眠不足は体温が原因? 冷えで眠れない人必見!「体温の下げ方」
- vol. 28パワーナップで午後の仕事もサクサク♪短い仮眠の実践法と3つのポイント
- vol. 29社会的時差ボケってどんなもの?休日の寝溜めが招く意外な悪影響とは
- vol. 30寝る直前に運動してはいけないって本当?眠りと運動の関係
- vol. 31スマホ不眠を防ぐ上手な使い方とは?快眠のためのポイント5つ
- vol. 32まさに「寝る子は育つ」。子どもの睡眠を守る5つのポイント
- vol. 33睡眠の質を落とす「NG生活習慣」とは?よく眠るための簡単セルフチェック
- vol. 34快眠のカギは寝室・寝具にあり。睡眠の質をUPする「睡眠環境」を整えよう
- vol. 35ロングスリーパー、ショートスリーパーの目安は?睡眠障害との見分け方も解説
- vol. 36「よく動く人」はよく眠る♪快眠のための運動で意識したい2つのポイント
- vol. 37【寝酒はNG】睡眠の質を下げない「アルコールとの上手な付き合い方」を解説
- vol. 38春夏秋冬で変わる睡眠の特徴とは?季節ごとの快眠のコツを解説
- vol. 39夜ぐっすり、朝スッキリ♪睡眠の質を上げる日光浴のコツ
- vol. 40快眠への第一歩!質の良い眠りを手に入れるための就寝前ルーティン
- vol. 41放置は危険。「睡眠負債」が引き起こす5つのリスクと対策のポイント
- vol. 42高齢者にとっての快眠術とは?睡眠の質を高める5つのポイント
- vol. 43交替制勤務(シフトワーク)でも健康を守る睡眠マネジメント法
- vol. 44寝ても疲れがとれない人必見!見落としがちな睡眠の質を下げる4つの生活習慣と改善策
- vol. 45「週末の夜ふかしにさようなら」睡眠リズムを無理なく整えるポイント
- vol. 46昼寝と夜の睡眠はどう違う?「分割睡眠」の特徴とリスクを解説
- vol. 47ひどい「いびき」は何故起きる?生活にひそむ意外な原因をチェック
- vol. 48足の冷えで眠れない時の「温め方」